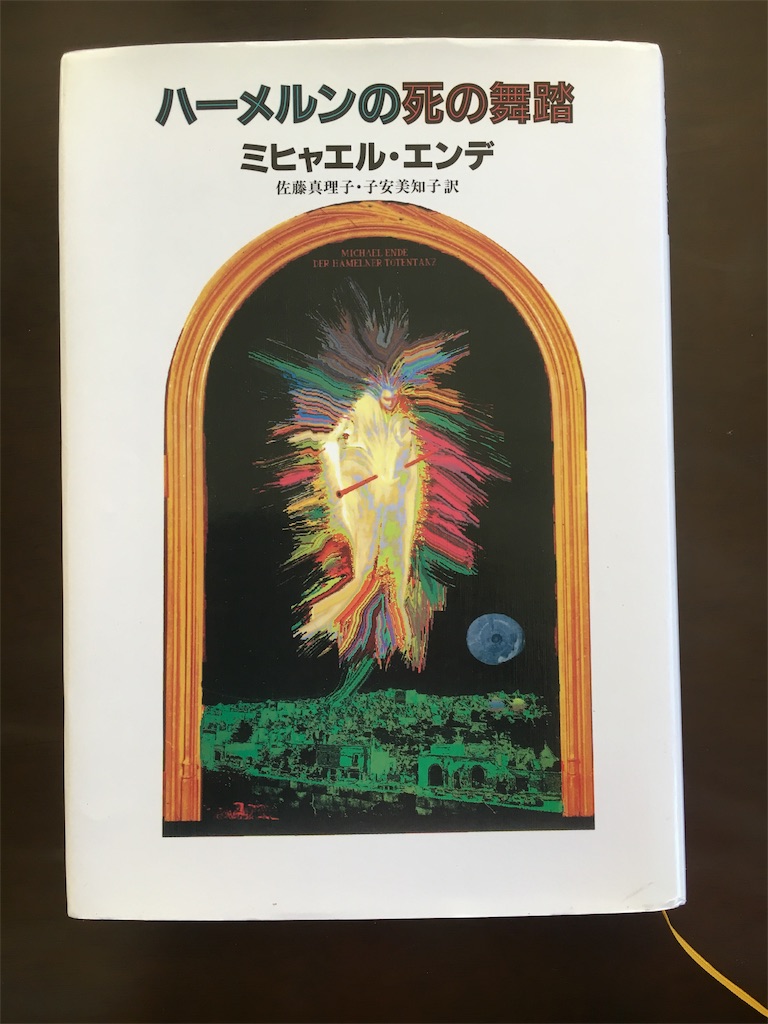
ミヒャエル・エンデの「ハーメルンの死の舞踏」を読みました。
エンデはドイツの作家さんです。
「モモ」という作品が特によく知られているようです。
友人にこちらの作品を教えてもらったので、「モモ」より先にこちらを読みました。
簡単に感想を書きたいと思いますが、少しネタバレしてしまうかも…。
なので、これから読む予定の方は、以下は読まないでね(о´∀`о)
☆☆☆
オペラの台本のような形式で書かれているので、さくさくと読み進めやすかったです。
ただ、ちょっと意味がわかりにくいところがあったので、本の「あとがき」に助けられました。
なんかね、たまに目にする「陰謀論」をガチで物語化したような、シュールな話だった。
お金持ちたちは「秘密」を共有していて、その「秘密」ってのは、お金を作り出す神さまなのね。
そして、その神様に忠誠を誓うための黒魔術的な儀式も「秘密」に含まれるの。
でも、その神様ね、お金を作ると同時に災いも一緒に作っちゃうという…。
こういう背景を、ハーメルンの笛吹き男の伝説と絡めたお話なのね。
「お金を得ることを第一目的に行動する」
ということに警鐘をならしたお話だと感じました。
もし、お金が行動を決定する第一の基準だとしたら、お金をくれる人が誰であれ、その人(または組織)に魂を売ることになるよね?
そして、お金を得る(作る)仕組みは、自分たちだけのヒミツにするよね。
で、仕組みを知らない人たち(=あまりお金を持たない人たち)にお金をちょっぴり「めぐんで」、良い人だと言われたりして、自分の行為を正当化する。
そして、人類全体の貧富の差は広がっていく。
こうした状況をストーリーの中で描くことで、現代社会をシュールに暗示しているように感じたわ。
あとね、お金を第一基準にする人が、世の中を支配している限り、「みんなが(金銭的に)豊か」な世界は絶対に訪れないということを、暗喩しているように感じたわ。
「あとがき」の助けがなければ、ちょっと理解しにくいところもあったけど、読んでよかったと感じたわ。
☆☆☆
私個人の意見としては、現代の日本で生きていくのに、お金はとても大切だと思う。
正直言って、お金は大好きだな( ´ ▽ ` )
でもね、私はお金を得ることを第一で行動しているわけではないな。
たとえ、どんなにお金を積まれたとしても、共感できる方からのオファーでなければお受けしない。お受けできないのよ。
逆にパッションが湧き起これば、依頼者がいるかどうかわからなくても、演奏会を企画してしまうわ。
それが、私の行動の原動力みたい。
ちょっと、本の感想から脱線してしまったわ。
今日はこのへんで。
お読みくださりありがとうございました( ´ ▽ ` )